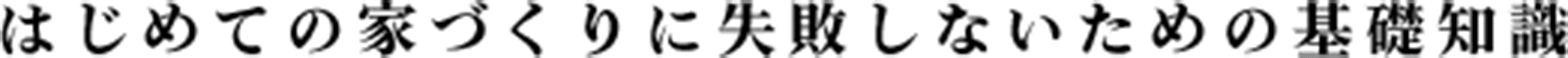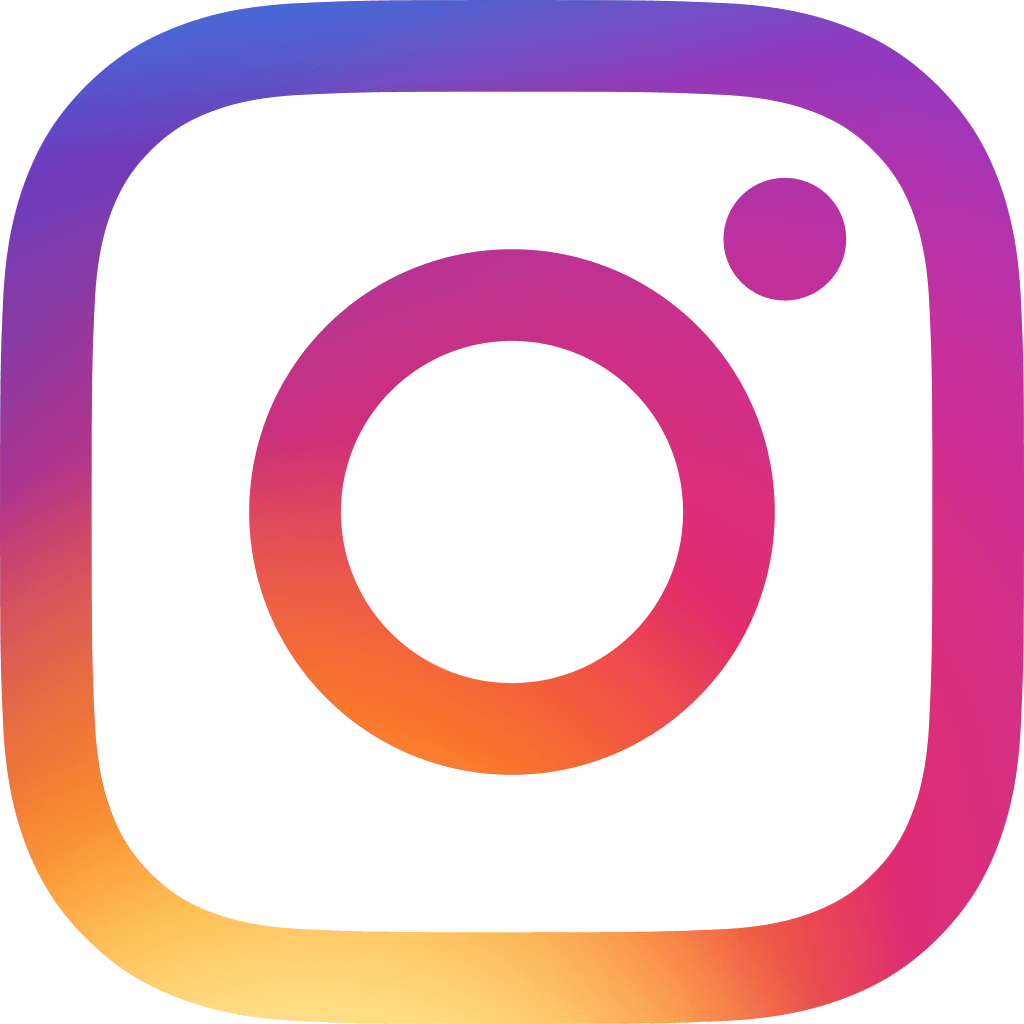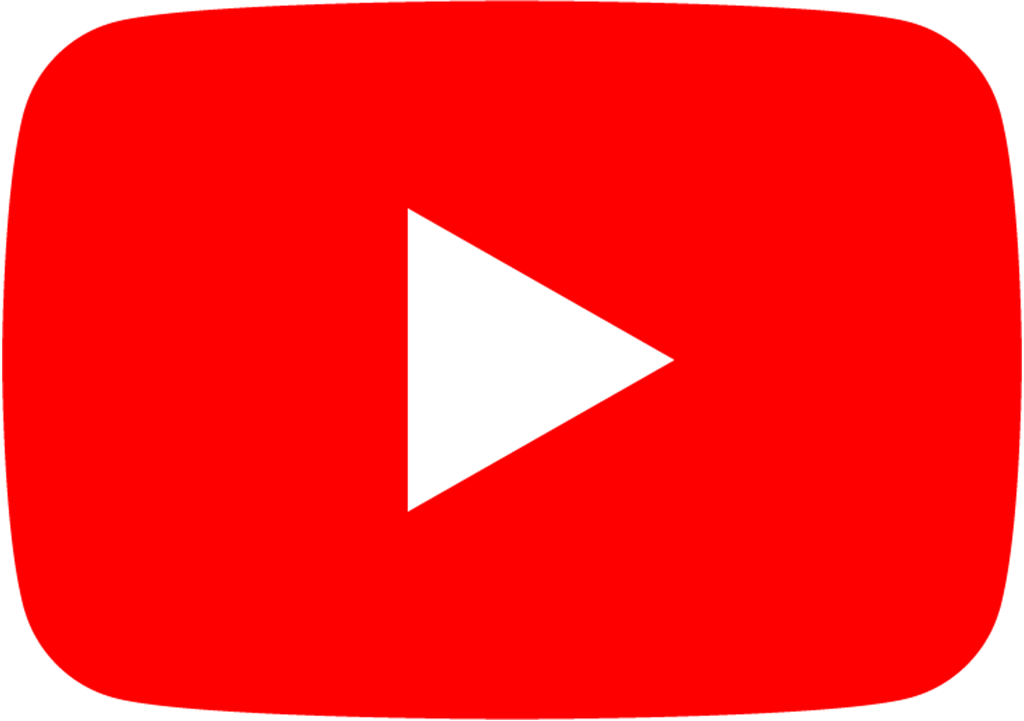◆「長く快適に住める家」に求められるのは“断熱性”
マイホームを建てるなら、できるだけ長く、快適に、そして省エネで暮らしたい――
そんな想いをかなえるのが「長期優良住宅制度」です。
長期優良住宅は、国が定める一定の基準を満たした“長持ちする高品質な住宅”のこと。
なかでも注目されるのが、断熱性能(断熱等性能等級)です。
断熱性能は家の快適性・省エネ性・健康性を左右する要素であり、
「冬暖かく、夏涼しい家づくり」の鍵を握っています。
2022年10月の制度改正によって、長期優良住宅の断熱基準が引き上げられ、
より高い水準の住宅が求められるようになりました。
この記事では、最新の改正内容を含めて、
長期優良住宅に必要な断熱等級・等級ごとの性能差・メリットを専門的にわかりやすく解説します。
◆長期優良住宅とは?国が認定する“長く良い家”の基準
長期優良住宅とは、国が住宅の品質向上と長期使用を促すために定めた認定制度です。
単に「新しい家」というだけでなく、「長く安全に住めること」を前提とした住宅で、
下記の要件を満たす必要があります。
-
劣化対策(構造材の耐久性を確保)
-
耐震性能(地震に強い構造)
-
省エネルギー性(断熱・気密性能)
-
維持管理・更新の容易性(点検・修繕しやすさ)
-
居住環境(周辺環境への配慮)
-
災害配慮(浸水・火災への対策)
- 住戸面積(長く快適に暮らせるか)
これらをクリアした住宅は、「長期優良住宅」として認定を受けることができ
税制優遇や補助金などの恩恵を受けられます。
またこの制度は、単に個人の住宅性能を高めるだけでなく
国全体の住宅ストックの品質を底上げする目的もあります。
しかし日本では住宅の平均寿命が30年程度と短く
欧米に比べると建替えサイクルが早いことが課題とされてきました。
長期優良住宅制度の導入によって、「良い家を建てて、長く大切に住む」という文化を根づかせ、
資産として価値が続く家づくりを促進する狙いがあります。
そのため、省エネ・耐震・メンテナンス性といった要素が重視されているのです。
🔹認定による主なメリット
-
住宅ローン控除の上限拡大
-
固定資産税の減税期間延長(通常3年→5年)
-
フラット35S(金利優遇)の利用
-
各種補助金(子育てグリーン住宅支援事業 など)
ただし、申請や設計・施工の確認などが必要で、
一般住宅よりも着工までに時間とコストがかかる点には注意が必要です。
◆断熱等性能等級とは?性能を数値で表す「UA値」の基準
断熱等性能等級(略して「断熱等級」)とは、
住宅の断熱性能を数値で評価する国の基準で、品確法(住宅の品質確保促進法)によって定められています。
この等級は、建物全体の「熱の逃げやすさ」を示すUA値(外皮平均熱貫流率)によって決まります。
UA値が小さいほど断熱性能が高く、熱が逃げにくい家ということです。
🔹断熱等性能等級の区分(2022年改正後)
| 等級 | UA値(6地域:東京・大阪など) | 性能の目安 |
|---|---|---|
| 等級4 | 0.87 | 旧省エネ基準(2015年までの一般基準) |
| 等級5 | 0.60 | ZEH基準(ゼロエネルギー住宅レベル) |
| 等級6 | 0.46 | 高断熱・高気密住宅 |
| 等級7 | 0.26 | 北欧並みの超高性能住宅 |
2022年10月の改正により、等級6・7が新設され、
これまでの「等級4が最高」という時代から、より高性能な住宅を目指す時代へと変化しました。
◆長期優良住宅の断熱等級は「等級5以上」が必須に
改正前は「等級4」でも認定可能でしたが、
2022年10月の改正後は「等級5(ZEH基準)以上」が必須条件となりました。
等級5は、断熱性能・省エネ性能が大幅に向上した住宅であり、
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)と同等水準の性能を持っています。
🔹ZEH住宅が満たす主な基準
-
断熱性能:等級5以上
-
一次エネルギー消費量:等級6以上
-
太陽光発電などでエネルギーを自給し、年間エネルギー収支をゼロ以下にする
この基準を満たすことで、冷暖房効率が大きく向上し、
真冬でも室温が9〜10℃を下回らない快適な環境を維持できます。
◆断熱等性能等級を上げるメリット
① 室内環境が快適になる
等級を上げる=UA値が小さくなるため、外気の影響を受けにくくなります。
夏は涼しく、冬は暖かく、エアコンの設定温度を抑えても快適に過ごせます。
冷暖房の効きがよくなるため、光熱費の削減にも直結します。
② 光熱費が削減できる
断熱性が高いほど冷暖房の使用頻度が減り、年間の光熱費が数万円単位で下がるケースも。
関西の気候で試算すると、等級4(旧基準)と等級5(ZEH基準)では年間約2〜4万円の節約効果が見込まれます。
③ 健康リスクを抑えられる
断熱性が低いと、部屋ごとの温度差でヒートショックや熱中症の危険が高まります。
断熱等性能等級を上げることで、室温の急激な変化を防ぎ、
高齢者や子どもにもやさしい住環境をつくることができます。
④ 建物の耐久性が向上する
断熱性能が高い家は、外気の影響を受けにくく、結露や湿気が発生しにくくなります。
これにより構造材の腐食を防ぎ、住宅の寿命を延ばす効果もあります。
⑤ 各種補助金・優遇制度を受けられる
高断熱住宅は、国や自治体の補助金対象になることが多く、
長期優良住宅+ZEH仕様にすることで、併用可能な支援制度もあります。
代表的なもの:
補助金制度の詳細は、【2025年版】子育てエコホーム支援事業の補助金まとめ
◆関西における断熱の重要性
How to Choose the Right Insulation for Your Home
断熱材の種類や特徴を比較しながら、家づくりで失敗しない選び方を解説
関西は、冬の底冷え・夏の高湿度といった「寒暖差の大きい地域」です。
京都や滋賀では冬の冷え込みが厳しく、和室中心の古い住宅では「隙間風による冷え」も問題でした。
一方で大阪や兵庫では夏の熱ごもりが強く、断熱性と通風の両立が欠かせません。
このような地域では、断熱材の厚み・窓の性能・気密施工の丁寧さが住宅の快適性を大きく左右します。
アーキホームライフでは、長期優良住宅基準以上の「等級7」を標準仕様とし、
ZEH水準の性能を確保するため、高性能断熱材+樹脂サッシ+Low-E複層ガラスを採用しています。
同じ関西でも、地域ごとに求められる断熱仕様は異なります。
たとえば、京都・滋賀などの内陸部では冬の底冷えが厳しく、窓まわりの断熱強化(トリプルガラス・樹脂サッシ)が有効です。
一方、大阪湾岸部や和歌山のように湿度が高い地域では、断熱材に加えて通気層や防湿シートの適正施工が重要になります。
アーキホームライフでは、各地域の気候データに基づき、最適な断熱仕様を選定。
「夏は涼しく、冬は暖かい」という理想の住環境を、エリア特性に合わせて実現しています。
◆省エネ断熱性能を高める3つの施工ポイント
断熱性能を上げるには、以下の3つの要素が重要です。
-
断熱材の性能と施工精度
グラスウール・吹付ウレタン・セルロースファイバーなど、素材特性に合わせて選定。
隙間なく施工することで性能を最大限に発揮できます。 -
開口部(窓・ドア)の性能
断熱性の弱点は窓です。複層ガラス・樹脂サッシ・断熱玄関ドアを組み合わせることで大幅に改善。 -
気密性の確保
高断熱でも気密が甘いと効果が半減します。C値(相当隙間面積)を低く抑えることがポイントです。
◆よくある質問(FAQ)
Q1. 長期優良住宅の申請は誰が行う?
A. 設計者や工務店などが申請を代行します。自分で手続きを行う必要はありません。
Q2. 等級5の家と等級7の家、体感でどれくらい違う?
A. 等級7は真冬でもほとんど冷暖房を使わずに快適。結露や温度ムラがほぼないレベルです。
Q3. 長期優良住宅にZEHは必須?
A. いいえ。ただし、ZEH水準の断熱等級(一次エネルギー消費等級6)を満たすことで、光熱費削減や補助金対象になります。
Q4. 建築コストはどのくらい上がる?
A. 等級4→5で建築費はおおよそ5〜10%上昇しますが、光熱費削減と税制優遇で数年で回収できます。
Q5. リフォームでも長期優良住宅にできる?
A. 一定条件を満たせば「長期優良住宅化リフォーム」として認定可能です。補助金対象にもなります。
◆今後の住宅性能基準の方向性
なお、国土交通省は2030年を目標に、全ての新築住宅でZEH基準相当の性能確保を掲げています。
今後は、断熱等性能等級5が“標準”となり、等級6〜7の住宅が「次世代型高性能住宅」として一般化していくでしょう。
つまり、これから家を建てる方にとっては、「今の基準を満たす家」よりも「将来も通用する性能の家」を選ぶことが、
長期的な資産価値と快適性の両立につながります。
断熱等性能を高めた家は、10年後・20年後も価値を保ち、光熱費や修繕費を抑える“経済的な選択”といえます。
◆まとめ|高断熱の家は“長持ちする家”。未来を見据えた住宅選びを
長期優良住宅は、単に「省エネな家」ではなく、家族が安心して長く暮らせる家を国が保証する制度です。
2022年の改正で求められる性能は高まりましたが、それは住宅の価値を高めるチャンスでもあります。
断熱等性能等級を上げることは、光熱費の削減だけでなく、健康・快適・資産価値の維持にもつながります。
これから家づくりを考えるなら、**「長期優良住宅 × 高断熱」**の視点を取り入れてみましょう。
アーキホームライフでは、関西の気候に最適化した断熱設計で、
快適で持続可能な住まいづくりをサポートしています。